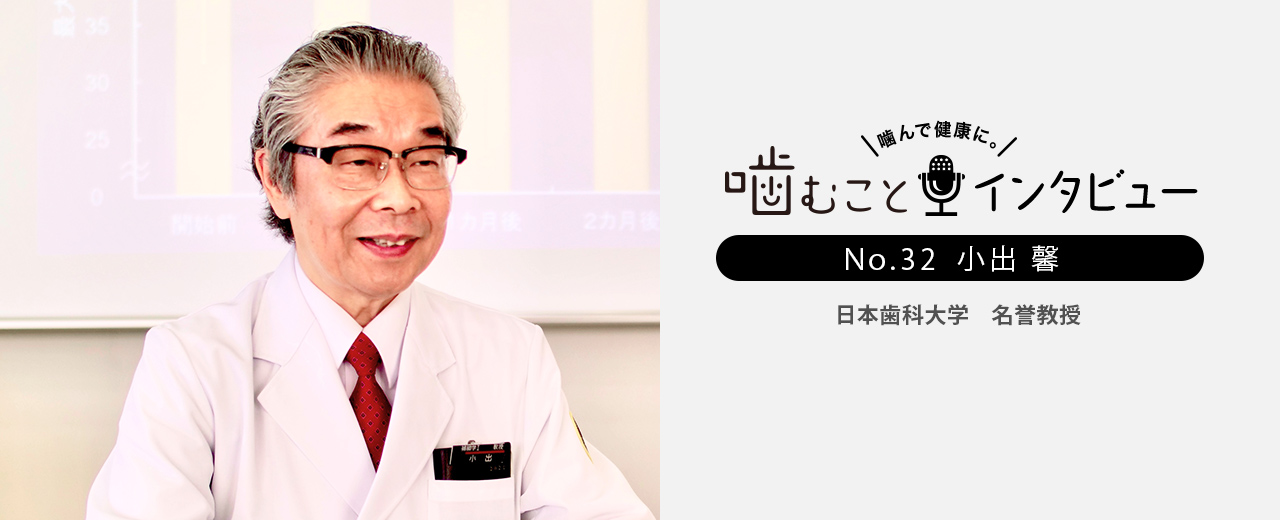超高齢社会の我が国では、長期介護・寝たきりの主要なリスク要因である「サルコペニア」の予防が重要な課題となっている。「サルコペニア」とは加齢や疾患により、骨格筋の筋量や筋力などの骨格筋機能が著しく低下し、身体機能に障害が生じた状態であり、日常生活動作の制限や転倒・骨折といった要介護につながるリスク要因など、さまざまな悪影響を引き起こすことが知られている。それでなくとも、日本を含むアジア人は欧米人に比べBMIの低い人(やせ型の人)が多く、生来の骨格筋量が少ないためサルコペニアに陥りやすいとされている。
サルコペニアは、2016年に国際疾病分類に登録されており、近年は「サルコペニア予防」の手掛かりとなる研究論文も多く公表されている。そうした中で注目されるのは、2024年1月に口腔衛生学会雑誌74巻1号にて、岡山大学(本部:岡山県岡山市)大学院医歯薬学総合研究科の研究グループが発表した『口腔状態とサルコペニアとの関連についての横断研究』(以下、本横断研究)である。
本横断研究では、岡山大学病院歯科・予防歯科部門を受診した60歳以上の患者を対象に、①年齢、②性別、③サルコペニア、④口腔状態、⑤栄養状態、⑥精神・心理状態、⑦全身疾患について調査した。特に、③サルコペニアと④口腔状態のデータを詳細に調べ、分析したところ、年齢の影響もさることながら、「舌の筋力が低下していると栄養状態が不良」であり、「サルコペニアの者が多い」傾向が浮き彫りとなった。

本横断研究は、舌の筋力とサルコペニアの興味深い関係性を示唆している。舌の筋力を維持することで、サルコペニアを予防し、ひいては長期介護・寝たきりのリスクを低減、健康寿命延伸の一助となる可能性を示している。
舌の筋肉を鍛える「ベロ回し体操」
ちなみに、ロッテ(本社:東京都新宿区)の公式サイト『噛むこと研究室』では、日本歯科大学の小出馨名誉教授が推奨する、舌の筋肉を鍛える「ベロ回し体操」「ベロ押し体操」「ベロ出し体操」を紹介している。
たとえば、「ベロ回し体操」は、唇を閉じて、上下の歯の外側にそって舌をぐるりと大きく「2秒に1回」のペースで回すというもの。これを時計回りと反時計回りに同じ回数行う。最初は5回ずつからスタートし、徐々に鳴らしながら回数を増やし、20回を目標にする。1日3度、毎食後に行うと良いという。「ベロ回し体操」は顔のたるみ改善のほか、血液循環の改善、自律神経の調整、免疫力の向上、若返りホルモン・パロチンの分泌促進などの効果があることも分かっており、精神的ストレスの軽減や脳へのよい刺激にもなるという(詳細は下記リンクを参照)。
厚生労働省の『令和2年版厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える』によると、2016年の日本人の平均寿命は男性80.98歳、女性87.14歳である。しかし、「健康寿命」については男性72.14歳、女性74.79歳であり、平均寿命とはそれぞれ約9年、約12年のギャップがある。つまり、男性は最後の約9年間、女性で約12年間を健康上の問題により、長期介護・寝たきりといった日常生活が制限されるリスクを内包している。そのリスク要因の一つである「サルコペニア」の予防は重要な社会課題であり、さらなる研究が望まれる。■
(La Caprese 編集長 Yukio)